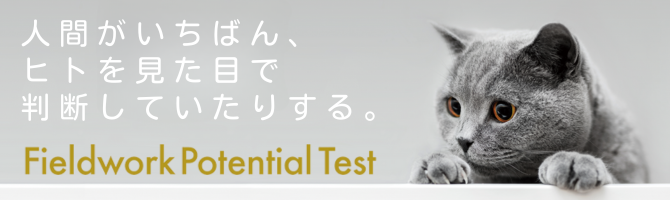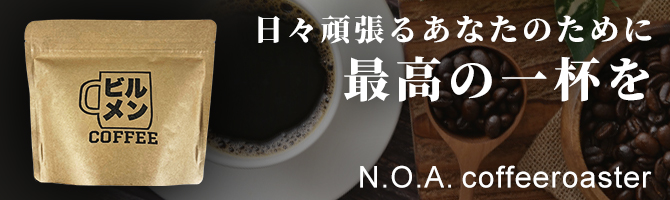汚れは見えるが、情報のゴミは見えにくい 〜ゴミ情報の選別で成長する清掃会社経営者のための実践術〜

清掃業を営むあなたは、毎日どのような情報を摂取していますか?
朝は新聞やテレビのニュース、昼休みはSNSのタイムライン、夜はYouTubeの経営者向けチャンネル…。情報があふれる現代社会で、私たちは常に「何かを知ろう」とし続けています。しかし、その情報の洪水が、かえって判断力を鈍らせていることにお気づきでしょうか。
清掃の現場では「見えない汚れを見つける目」が価値を生みます。同様に、情報社会では「本当に必要な知識を見分ける目」が経営者としての価値を高めるのです。
1. 情報という綱渡り:真実と秩序、どっちも大事でどっちも厄介
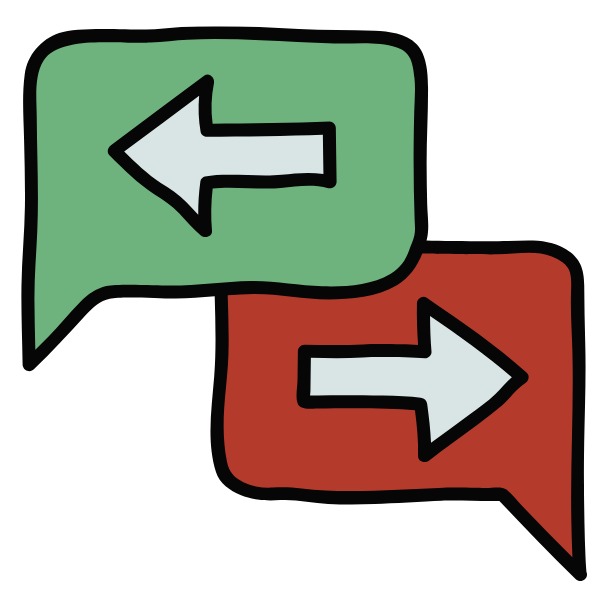
歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリは『NEXUS 情報の人類史』で以下のように指摘しています。
「人間の情報ネットワークの歴史は、進歩の大行進ではなく、真実と秩序のバランスを取ろうとする綱渡りだ。」
補足すると以下のようになります。
「人間の情報ネットワークの歴史とは、真実を追い求める知的探究と、社会秩序を維持する物語の創造という、しばしば相反する二つの使命の間で綱渡りを続けてきた歩みである。」
情報はいつの時代も、真実の発見と秩序の安定という二つの目的を担ってきました。つまり情報には、"正しいことを見つける力"と"みんなを納得させて動かす力"という二刀流が求められるのです。しかし、この真実と秩序という二つの要素は、時に対立することがあります。例えば「地球は回っている」という真実は、かつて「教会の秩序」を揺るがし、今日でも、進化論やワクチンが「人々の信じる秩序」と衝突し続けています。
物語は、必ずしも真実とは限りませんが、多くの人が信じることで秩序や協力を生み出す力を持っています。神話、宗教、国の理念、会社の方針がその代表例です。
一方で、科学や論理による真実の探究がなければ、社会は誤った信念に縛られ続けたでしょう。これは優劣の問題ではなく、真実と物語の両方が、社会を支えてきたのです。
このバランスが崩れると、社会は不安定になります。だからこそ、この綱渡りは今なお続いているのです。この洞察は、清掃会社経営にも直接つながります。私たちは常に二つの「情報の見方」の間で揺れ動いているのです。
現場の真実
「この方法では効率が悪い」「この価格設定では利益が出ない」
会社組織の秩序
「でも、皆がこのやり方に慣れている」「お客様はこの価格に納得している」
理想を追求しすぎれば現場が混乱し、現状維持に固執すれば革新が止まります。清掃業こそ、この「真実と秩序のバランス」が問われる業界なのです。
2. 情報レシピの選び方:「辛さだけのカレー」にご注意

現代の情報環境を「カレー」に例えると、こう表現できます。新聞やテレビは「伝統の味」としての地位にしがみつき、一方でSNSやYouTubeは「スパイス強めのトレンドカレー」として存在感を示しています。
オールドメディア(テレビ・新聞)
例えば「昔ながらの給食カレー」:安定感のある味わいを持つ一方で、物足りなさを感じたりする。懐かしい思い出があるが、たまに「ルーだけ」なんて日も。
ニューメディア(SNS・YouTube)
例えば「激辛インスタ映えカレー」:視覚的インパクトと刺激はあるものの、栄養バランスが偏り、「辛さだけ」が先行。派手さはあるけれど「米と合わない」ことも。
どちらも極端になると「真実の栄養」も「秩序という胃袋」も満たされません。つまり、深みのない味付けや、ただ辛いだけのカレーでは、本当の満足は得られないのです。
清掃業の経営者として、どちらか一方に依存するのは危険です。理想は「伝統的な安定と新しい視点の両方を取り入れた、バランスの良いカレー」。つまり、複数の情報源から「我が社に合う栄養素」を見極め、自社だけの「情報レシピ」を作ることが重要なのです。
3. 情報の限界効用:情報の“おかわり”にご注意

経済学には「限界効用逓減(ていげん)の法則」という原則があります。これは「1杯目のビールは格別においしいが、2杯目、3杯目と飲むごとに、その満足度は徐々に低下していき、最後は惰性で飲むようになる」という現象です。
この法則は情報にも当てはまります。ニュースアプリを次々と開き、SNSのトレンドを追い続け、YouTubeの動画を延々と見続けるうちに、「何が真実か」も「なぜ情報を集めているのか」も分からなくなってしまう状態に陥ったことはありませんか。
情報の摂取が過剰になると、かえって判断力が鈍ってしまうのです。さらに、SNSの「いいね」や通知は脳内でドーパミンを分泌させ、際限のない情報探索行動を引き起こすことが知られています。そのため、これらのメディアの使用は必要最小限に抑えることが重要です。
4.清掃会社経営者こそ、"情報という食材を吟味"せよ!

あなたの会社が真に必要としているのは、他人の"成功カレー"のレシピではありません。TikTokで流れる「バズる社長術」や、テレビの「昭和な成功談」に、どれほどの本質的な価値があるでしょうか。重要なのは「自社の実情に合った情報」「社員が理解しやすいストーリー」「確実な収益につながる判断材料」です。情報は料理と同じです。どんなに良いスパイスを使っても、材料(=現場の実情)が悪ければ、料理は美味しくなりません。
・1つでも「現場に活かせる情報」
・1つでも「人が辞めない工夫」
・1つでも「失敗を避けられる知識」
これらがあれば、100の知識よりも強力な武器になります。
清掃業に特化した「情報フィルタリング」の基準として、具体的には次のようなものが挙げられます。
1. 現場適用性フィルター
「この情報は、明日からの現場オペレーションに活かせるか?」
例:新しい洗剤の知識、効率的な清掃順序、スタッフ教育のコツなど
2. 持続可能性フィルター
「この情報は、一時的なブームではなく、長期的な価値があるか?」
例:人材定着のための仕組み、リピート顧客を増やす方法など
3. 差別化フィルター
「この情報は、他社と差をつけるために役立つか?」
例:特殊清掃のノウハウ、独自の品質管理システムなど
5. 真実と秩序のバランスを取る経営者が、最終的に強い
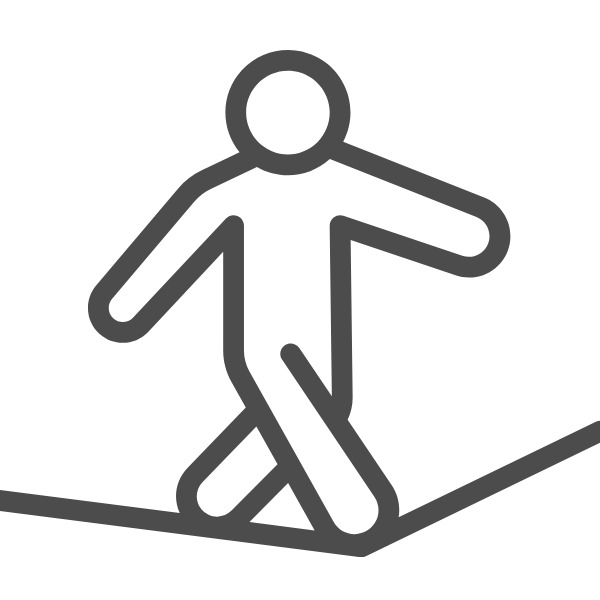
清掃業界は今、大きな転換期を迎えています。
- 人手不足による人材確保の難しさ
- 人件費および資機材コストの上昇
- SDGsなど環境配慮への社会的要請
- コロナ後の新たな衛生基準への対応
- 高齢化に伴う特殊清掃ニーズの増加
- デジタル化によるニーズの多様化
この変化の時代に、「情報の綱渡り」が経営者としての真価を問うのです。
・真実ばかりを追求すれば、現場が置き去りになる(理想主義)
・秩序のみを重視すれば、成長が止まってしまう(保守主義)
真の経営者力とは、この二つのバランスを取りながら、「変えるべきもの」と「守るべきもの」を見極める眼力です。そしてこれからの清掃業界のリーダーには、その判断を現場スタッフやお客様に「納得感のあるストーリー」として伝えられる能力が不可欠です。
まとめ:情報の「摂取と見極め」も経営の重要な一部
清掃のプロは「汚れを取り除く」ことで価値を生み出します。同様に、情報時代の経営者は「無用な情報を取り除く」ことで判断力を高めます。毎日の情報摂取にも、以下の「清掃の三原則」を当てはめてみましょう。
1. 見えないところこそ丁寧に
華やかな成功事例の裏に隠れたリスクや前提条件を見極める
2. 適切な道具を選ぶ
自社の状況に合った情報源を厳選する
3. 定期的なメンテナンス
古くなった知識や前提を捨て、定期的に情報を更新する
清掃業界こそ、「情報を制する者が未来を制する」時代です。日々の喧騒に流されず、自らの頭で考え、自らの言葉で伝え、自らの会社を強くしていきましょう。
|◤あとがき◢|
「汚れは見えるが、情報のゴミは見えにくい」
清掃のプロであるあなたなら、この言葉の意味がよくわかるはずです。目に見えない汚れを感覚で捉える技術が清掃の真髄であるように、有益な情報と無益な情報を直感的に見分ける力が、これからの経営者には求められます。情報過多で疲れを感じたときは、あなたの会社が大切にしている「清掃の哲学」に立ち返ってください。不要なものを丁寧に取り除いていけば、本質的な価値は自ずと輝きを放つはずです。